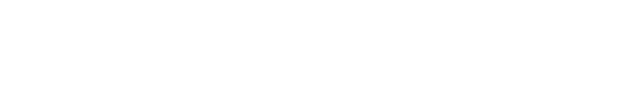インフルエンザワクチンって本当に効くのでしょうか?
この季節になると「毎年ワクチンを打っているのに、毎年罹るのですが、本当に効いているんでしょうか?」と云う質問をよくされますが、私たちはいつも「打っていたからその程度に済んだのでしょう。打っていなければもっと大変だったと思いますよ。」と答えています。
本当にそうでしょうか。 確かに個人がワクチンによってどの程度守られているかを実感することは難しいと思いますが、多くの疫学的研究からも、社会全体がワクチンにより守られている事は証明されています。 今回の話題は、いささか古いデータではありますが、「学童へのワクチン接種が、お年寄りの死亡数の減少に寄与する」事を証明した論文を紹介します。
まずその前に右の図を説明します。これは1996年の厚生省(現厚労省)発表のデータです。縦軸が死亡率、横軸が年齢で、インフルエンザの罹患率は、乳幼児期にピークがあり、死亡率は、圧倒的に高齢者で高いと云う事を示しています。即ち子供は罹りやすいけれど、一部を除いて、重篤な状態になることが少ない反面、高齢者はインフルエンザに罹ることをきっかけとして、肺炎や持病の悪化により亡くなる確率が高いという事なのです。
次の図の説明に移ります。日本では、1957年のインフルエンザの大流行(アジア風邪)を契機に、1962年から学童にインフルエンザワクチンの接種が始まり、1977年には、これが定期接種へと格上げされました。この政策は1986年まで続きましたが、父兄の反対などで1987年から一部緩和され、更に1994年には、効果に対する疑問や、副作用への過剰な懸念から任意接種へと変わり、本邦でのワクチン接種率は急速に低下しました。これに対して、欧米先進国では、ワクチンの重要性に対する認識が高まり、ワクチンの接種率は急速に上昇しました。 右の図は、1980年から1995年の間の各国のワクチン接種数を並べたものです。 左上が日本、その右隣が米国、その隣からスペイン、カナダ等が並んでいます。すなわち日本が急速に数を減らしている中で、その他の先進国ではこの間にワクチン接種数が大幅に伸びている事を表しています。
こうした状況を踏まえて、医学系研究で最も権威のある雑誌の一つであるThe New England Journal of Medicine に載った論文(Vol.344, No..12-March 22, 2001)は注目すべきものでした。
日米のワクチン政策の変化と、インフルエンザに関連する死亡数の変化について考察した論文で、ワクチンの有効性を示す疫学的研究で最もインパクトのある研究の一つと考えられています。
この論文の核心の部分を示す図が右側で、上の図は日本、下は米国のデータで、横軸は西暦、縦軸は数(率)を表しています。曲線は、全ての死亡者の数の推移(平均)を表しています。折れ線グラフは超過死亡(大きな疫学的イベントで死亡者が予測を超えて増えた事を意味し、その大部分はインフルエンザおよびインフルエンザ感染に起因した死亡と考えられています)を表します。更に縦の棒はワクチン接種数を示しています。1950~1960年、特に1957年のアジア風邪(インフルエンザ)の大流行では、超過死亡(折れ線)が平均(曲線)を大きく上回っている事が理解されます。その後日本(上の図)では1962年から学童へのインフルエンザワクチンの定期接種が始まり、ワクチン接種数(棒ブラフ)が伸びるに従い、超過死亡(折れ線)の平均死亡(曲線)からの乖離が少なくなって行き、1987年のワクチン政策の変更を機にワクチン接種数(棒)の減少と、超過死亡(折れ線)の平均死亡(曲線)からの乖離が大きくなって行った事が読み取れます。一方の米国では、右肩上がりに上昇し、それに連れて、超過死亡の平均死亡からの乖離が少なくなっていることがわかります。
即ち、日本に於ける学童へのワクチン接種が、社会全体としての死亡数の減少に寄与していたと証明できる訳です。
勿論30年〜40年前のデータの再現は核家族化の進んだ現代では難しいでしょうし、今は65歳以上の高齢者へのワクチン接種が補助されています。しかしこうした流れの根底には、ワクチンは個人を守るだけではなく、集団(社会)を守るために有用であると云う思想が流れている訳です。
それにしても1950~1960年代当時、世界をリードするインフルエンザとの闘いを主導した日本の研究者、医師、行政の担当者等の気概を感じるデータだと思いませんか。